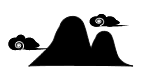×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
君は、春を呼ぶ花
片倉小十郎は伊達政宗の側近の中でも誰よりも彼の信頼が厚く、彼の傍に控えている武将である。まだ幼かった政宗を己が主人と定め、どんな時も支えて来た。伊達軍の者達ならそれはよく知っていることで、誰もそんな当たり前のことを言うことはない。だからいつきはしばらくの間、それを知らなかった。それでも政宗が彼を誰よりも信用しているのは、彼等の傍で暮らしているうちに判ってくる。
いつきから見れば政宗も充分に大人で、それよりも更に落ち着きがあってどっしりと構えている小十郎は、遠い大人の男の人だった。
もともと人とあまり付き合いのなかったいつきは、そんな彼に慣れるのにも少しだけ時間がかかった。悪い人ではないと判っていても、大きな男の人。更に言えば、政宗もそうなのだが、どうにもその鋭い目つきなどが威圧感を感じさせる。もっとも、「侍」の元締のような「殿様」である政宗よりは先に打ち解けたのだが・・・
いつきが小十郎に打ち解けることが出来るようになったきっかけは、彼の趣味でもある「野菜作り」だった。食事を運んで来てくれるのはたいてい台所の者か顔見知りになった女中だったのだが、時たま政宗が自分の分と一緒に持って来たり、まれに、小十郎が政宗の言づてと一緒に持って来てくれるようになって、少しずつ言葉を交わすようになって、そうやって城の者達と慣れていくにつれ、彼等とも話すことが出来るようになった。
もっとも、いつきも案外人懐っこい性格だったので、彼等と自然と言葉を交わすようになるまではそう時間はかからなかった。
そんな中で、小十郎が自分で畑を耕し、野菜を育てていることを聞いた。その頃には毎日ただ城の中でぼーっとしているのが苦痛になってきていたいつきは、自分もそれがやりたい。と、初めて自分から人に何かをしたい。と頼んだのだ。
小十郎もそれに異存はなかったのだが、いつきは彼の主人が連れて来た客人のようなものだ。自分の一存では決められないから、政宗様に一応、お断りを入れておけ。とだけ言っておいた。
小十郎から言っても良かったのだが、それよりも、彼女が政宗に自分から頼んだ方がいい。そう思ったのだ。
そうしていつきはしばらくして、政宗から許可を貰った。といって、政宗が用意してくれた道具を手に、小十郎の畑に顔を出すようになった。
冬の厳しい奥州では、雪が辺り一面を埋め尽くす日々が続く。幸いにもここ最近は戦の話もなく、そんな中、わずかな晴れ間を見つけては、二人は畑に出て様子を見ていた。
外に出るようになって、いつきは元気が出て来たようだった。小十郎ともよく話すようになり、少しずつ明るくなっている。
こんな小さな子供が一人で生きてきたのだと思うと、小十郎も考えてしまうことが多い。彼が初めて出会った頃の政宗より歳はいってはいるが、城の中で最低限のものは保証されていた彼とは違い、この少女は、一人きりで食べるために働き、生きるために耐えてきたのだ。
どちらの方が辛い。というのではない。それは比べられるものではない。けれどその話を聞いて、彼女を目の前にした時に、幼い頃の主人の姿を思い出した。
政宗とは違う。けれどこの少女もどこか、暗い陰を思わせる。それが少しずつ、明るい表情を見せてくれるようになってきた。それが素直に嬉しいと思う。
「小十郎さは、殿様の側近なんだべ」
「そうだな。幼い頃から、お傍に仕えさせていただいている」
ある日のこと、いつものように畑に出る途中、そんなことを訊かれた。
「じゃあ、殿様に秘密は出来ねぇんだな」
「何だ?知られちゃ具合の悪いコトでもあるのか?」
何でもねぇ。と慌てたように頭を振る姿を見れば、何か隠していることがあるのだとすぐに判る。
「まさか、逃げようとかそういうことじゃねぇだろうが・・・」
小十郎の畑は城を出て少しはずれた場所にあって、そこに行くには城を出ることになる。別に捕虜というわけでもないのだが、今いつきが逃げ出して、彼女の存在が外に知れるのはあまり具合のいいことではない。何しろ彼女は死んだことになっているのだ。一揆鎮圧からまだそう時間も経っていない。銀色の髪の少女の記憶が世間から薄れるまでは、おおっぴらに外に出られては困る。
「違うだ!そうでなくて・・・」
殿様には、秘密にしてくれるだか?と、見上げて聞くその表情には、裏がない。
「内容にもよるな」
主人に害を為すことでなければ、何も小十郎だって、一から十まで、いつきの行動を政宗に報告したりはしない。
「こっち」
小さな手が小十郎の手を取る。初めて触れた少女の手の感触に、思わず驚いてしまった。
なんて小さい・・・
いつきは、おそらく同じ歳のどの子供よりも小さく見える。一人きりで食うや食わずで生きて来たのだから、それも仕方がないのかもしれない。細くて小さなその姿を最初見た時には、十に満たないとも思ったくらいだ。それは政宗も同じだったようで、だからいつきが少しでもたくさん食べられるようにと、何かと台所に声をかけているのを小十郎は知っている。
そんな小さな手に引かれ、畑よりもまた少し離れた林の中を歩く。普段からそんなに目を離したつもりはなかったのだが、いつの間にこんな処にまで足を運んでいたのだろう。と思った時、足が止まった。
「良かった・・・まだ誰にも採られてねぇだ」
ほっとしたような声。そして手が離れ、いつきがその場にしゃがみこむ。
「な?あと少しで花が咲くんだ。それまでは、殿様には黙っててけろ」
少女の足元には、雪の中から力強く顔を出す緑色の葉。
「福寿草か」
「?マンサクじゃねぇだか?」
「元日草。とも言うな。よく見つけたな」
んだ。春を呼ぶ花だ。と、誇らしげにいつきは笑う。
「春を呼ぶ・・・か、上手いこと言うな」
これが咲いたら、殿様に見せてやるんだ。と、つぶやくその表情を見て、小十郎はほっとした。ずっとどこか寂しそうな、悲しそうな目をしていた少女が、確かに成長している姿を見られた気がしたのだ。
政宗の時もこの少女も、子供があんな目をするのを見たくはない。と思う。おそらくはあまりにも聡く、そのために周りの者達を見て、悟ってしまう。そうして聡いが為に己を殺す。本来子供ならば知らずに済むことを、幼い頃に知ってしまった者同士。おそらくは政宗も、それをこの少女に見たのだろうと今なら判る。
「だから、それまでは秘密にしてくんろ」
教えたのは、小十郎さだけなんだ。と言う言葉に、この少女が心を開いてきてくれていることを感じて嬉しく思う。
「判った。その日までは、政宗様にも黙っておく」
ほら。と小指を差し出せば、いつきは不思議そうにそれを見つめ、それから小十郎の目を見た。
「ゆびきり。だ」
おずおずと、いつきの手が伸ばされる。その手を取って、小指を絡めた。
「小十郎さは、何でも知ってんだな」
おそらく、こうして誰かと約束を交わすのも初めてなのだろう。いつきは嬉しそうに微かに頬を赤く染めて、ゆびきりげんまん。と呟いた。
「何だよ小十郎、いやに機嫌がいいみたいじゃねぇか」
「そうですか」
そうだよ。と返して、政宗はいぶかしく思う。そういえば今日はいつきも、どこか機嫌が良かったように思う。二人は午前中に連れだって小十郎の畑に行ったと思ったのだが、それで何故、揃って機嫌がいいのかが判らない。
「何かあったのか?」
多少の皮肉も込めて愛想よく聞いてみれば、ふっ、と小さく笑われた。
「What?」
馬鹿にされた訳ではないのだろうが、なんだか面白くない。しかし小十郎はそれに気付いているのかいないのか、すぐに判りますよ。とだけ言い残し、下がってしまった。
「何なんだよ、一体・・・」
何だかおいてけぼりにされたような心持ちで、八つ当たりするかのように、政宗はやや乱暴に筆を走らせた。
パタパタと軽い足音が廊下から聞こえる。今この城の中であれだけ軽い足音をさせるのは一人しかいない。何があったんだ。と思いつつ、その足音を聞いていると、今度は遠くから、いつきの声と小十郎の声がする。
「・・・何だよ」
二人が最近打ち解けてきているのは知っていたが、走って行くほどにいつきが彼を慕っているとは思わなかった。いつの間にそんなに仲良くなったんだ?と思う反面、なんだか一人仲間はずれにされたような疎外感も少なからずある。
「政宗様」
声をかけられても素直に出る気になれずに、わざとのろのろと襖を開ける。
「少し外に出られてはいかがでしょう」
涼しい顔でそう言う小十郎の後ろに隠れるようにいつきがいて、一体何企んでんだか。と思いながらも、政宗は二人について行くことにした。
二人の後をついて歩いていると、一度ここまで来ていたのか、雪の上に小さな足跡が先に続いているのが見えた。
「一人で歩き回ってたのか?」
何気なく聞いてみれば、いつきは申し訳なさそうに俯いて小さくうなずく。別にそんなに怯えなくとも。と思うのだが、もしかしたら、気付かないうちに不機嫌なのが声に出ていたのかもしれない。
「殿様、こっちだべ」
いつきが指さす先を向けば、白い雪の中に浮き上がるような色が見えた。
「へェ・・・Adonis か」
黄色い花が、雪の中から顔を出している。雪に埋もれるこの地で、白と黒以外の色を見られる機会はそう多くはない。
「こりゃ縁起がいいな」
軽く口笛を吹いてそう言えば、嬉しそうにいつきが笑う。
「気に入ってくれただか?」
Yes. とうなずけば、少女は寒さで赤くなった頬を両手で包むようにしながら、笑顔を返してくれた。
「良かっただ〜」
苦笑して、その銀色の髪をくしゃくしゃと撫でる。これを見せるために、寒いのに朝からここに来たのだろう。頬も鼻の頭も赤くなっている。
「とにかく一度帰って、あったまった方がいいな」
しばらく雪の中に咲き誇る花を見ていたが、そう言っていつきを促す。城に戻れば、温かい甘酒が用意されていた。どうやら小十郎が、出かける前に台所に伝えていたらしい。
「・・・で、何で黙ってた」
「お気付きでしたか」
「そりゃあな」
ここ数日、いつきが上機嫌だったりそわそわと落ち着かなかったりした原因があれだとすれば、しょっちゅう小十郎の元を訊ねていた理由も判ってくる。第一、いつきと一緒に外に出る人物なんて、今のところかなり限られているのだ。
「約束をしましたから」
へぇ。と、つぶやくように返して、それから政宗は座り込んだままむすっとしたように、窓の外を眺める。
「どうかしましたか?」
「あいつ、お前のことは小十郎って呼ぶんだよな」
それは政宗様や他の者がそう呼ぶからでしょう。というのはもっともで、しかしなんだか納得がいかない。
「殿様。と呼ばれるのは嫌ですか」
「・・・それか」
城の者達は、城の中では政宗のことを殿様。とはあまり呼ばない。政宗様。と呼ぶ。いつきはいつだって、一呼吸おいてから「殿様」と呼ぶ。おそらくは「お侍さん」と咄嗟に呼んでしまいそうになるのだろう。よく言い直しているのも知っている。
「殿様なんて、どうも堅苦しくていけねぇ」
そうかそうか。と、一人頷いている政宗を見ながら、小十郎は微かに込み上げて来る笑いを抑えた。
その日、いつきは政宗直々に「殿様と呼ぶのは禁止」と言い渡された。それなら。と、小十郎達と同じように「政宗様」と呼んだら、それも堅苦しいから、呼び捨てでいいぞ。と言う。
少し困ったのだが、子供が遠慮するな。と押し切られてしまった。しかし実際口にしてみれば、成程確かに、それが何よりも彼なのだ。と思えたから、その日からいつきは政宗のことを「殿様」と呼ぶのをやめた。
いつきが政宗に福寿草を見せてあげる話を書きたい。というのがきっかけだった筈なんですが⋯途中からなぜかこじゅいつ風味(?)に・・・
この前の外伝3は、この後の頃の話になりますね。
お侍→殿様→政宗
と、慣れてくるにつれ、呼び方が変わっているということで。
いつきから見れば政宗も充分に大人で、それよりも更に落ち着きがあってどっしりと構えている小十郎は、遠い大人の男の人だった。
もともと人とあまり付き合いのなかったいつきは、そんな彼に慣れるのにも少しだけ時間がかかった。悪い人ではないと判っていても、大きな男の人。更に言えば、政宗もそうなのだが、どうにもその鋭い目つきなどが威圧感を感じさせる。もっとも、「侍」の元締のような「殿様」である政宗よりは先に打ち解けたのだが・・・
いつきが小十郎に打ち解けることが出来るようになったきっかけは、彼の趣味でもある「野菜作り」だった。食事を運んで来てくれるのはたいてい台所の者か顔見知りになった女中だったのだが、時たま政宗が自分の分と一緒に持って来たり、まれに、小十郎が政宗の言づてと一緒に持って来てくれるようになって、少しずつ言葉を交わすようになって、そうやって城の者達と慣れていくにつれ、彼等とも話すことが出来るようになった。
もっとも、いつきも案外人懐っこい性格だったので、彼等と自然と言葉を交わすようになるまではそう時間はかからなかった。
そんな中で、小十郎が自分で畑を耕し、野菜を育てていることを聞いた。その頃には毎日ただ城の中でぼーっとしているのが苦痛になってきていたいつきは、自分もそれがやりたい。と、初めて自分から人に何かをしたい。と頼んだのだ。
小十郎もそれに異存はなかったのだが、いつきは彼の主人が連れて来た客人のようなものだ。自分の一存では決められないから、政宗様に一応、お断りを入れておけ。とだけ言っておいた。
小十郎から言っても良かったのだが、それよりも、彼女が政宗に自分から頼んだ方がいい。そう思ったのだ。
そうしていつきはしばらくして、政宗から許可を貰った。といって、政宗が用意してくれた道具を手に、小十郎の畑に顔を出すようになった。
冬の厳しい奥州では、雪が辺り一面を埋め尽くす日々が続く。幸いにもここ最近は戦の話もなく、そんな中、わずかな晴れ間を見つけては、二人は畑に出て様子を見ていた。
外に出るようになって、いつきは元気が出て来たようだった。小十郎ともよく話すようになり、少しずつ明るくなっている。
こんな小さな子供が一人で生きてきたのだと思うと、小十郎も考えてしまうことが多い。彼が初めて出会った頃の政宗より歳はいってはいるが、城の中で最低限のものは保証されていた彼とは違い、この少女は、一人きりで食べるために働き、生きるために耐えてきたのだ。
どちらの方が辛い。というのではない。それは比べられるものではない。けれどその話を聞いて、彼女を目の前にした時に、幼い頃の主人の姿を思い出した。
政宗とは違う。けれどこの少女もどこか、暗い陰を思わせる。それが少しずつ、明るい表情を見せてくれるようになってきた。それが素直に嬉しいと思う。
「小十郎さは、殿様の側近なんだべ」
「そうだな。幼い頃から、お傍に仕えさせていただいている」
ある日のこと、いつものように畑に出る途中、そんなことを訊かれた。
「じゃあ、殿様に秘密は出来ねぇんだな」
「何だ?知られちゃ具合の悪いコトでもあるのか?」
何でもねぇ。と慌てたように頭を振る姿を見れば、何か隠していることがあるのだとすぐに判る。
「まさか、逃げようとかそういうことじゃねぇだろうが・・・」
小十郎の畑は城を出て少しはずれた場所にあって、そこに行くには城を出ることになる。別に捕虜というわけでもないのだが、今いつきが逃げ出して、彼女の存在が外に知れるのはあまり具合のいいことではない。何しろ彼女は死んだことになっているのだ。一揆鎮圧からまだそう時間も経っていない。銀色の髪の少女の記憶が世間から薄れるまでは、おおっぴらに外に出られては困る。
「違うだ!そうでなくて・・・」
殿様には、秘密にしてくれるだか?と、見上げて聞くその表情には、裏がない。
「内容にもよるな」
主人に害を為すことでなければ、何も小十郎だって、一から十まで、いつきの行動を政宗に報告したりはしない。
「こっち」
小さな手が小十郎の手を取る。初めて触れた少女の手の感触に、思わず驚いてしまった。
なんて小さい・・・
いつきは、おそらく同じ歳のどの子供よりも小さく見える。一人きりで食うや食わずで生きて来たのだから、それも仕方がないのかもしれない。細くて小さなその姿を最初見た時には、十に満たないとも思ったくらいだ。それは政宗も同じだったようで、だからいつきが少しでもたくさん食べられるようにと、何かと台所に声をかけているのを小十郎は知っている。
そんな小さな手に引かれ、畑よりもまた少し離れた林の中を歩く。普段からそんなに目を離したつもりはなかったのだが、いつの間にこんな処にまで足を運んでいたのだろう。と思った時、足が止まった。
「良かった・・・まだ誰にも採られてねぇだ」
ほっとしたような声。そして手が離れ、いつきがその場にしゃがみこむ。
「な?あと少しで花が咲くんだ。それまでは、殿様には黙っててけろ」
少女の足元には、雪の中から力強く顔を出す緑色の葉。
「福寿草か」
「?マンサクじゃねぇだか?」
「元日草。とも言うな。よく見つけたな」
んだ。春を呼ぶ花だ。と、誇らしげにいつきは笑う。
「春を呼ぶ・・・か、上手いこと言うな」
これが咲いたら、殿様に見せてやるんだ。と、つぶやくその表情を見て、小十郎はほっとした。ずっとどこか寂しそうな、悲しそうな目をしていた少女が、確かに成長している姿を見られた気がしたのだ。
政宗の時もこの少女も、子供があんな目をするのを見たくはない。と思う。おそらくはあまりにも聡く、そのために周りの者達を見て、悟ってしまう。そうして聡いが為に己を殺す。本来子供ならば知らずに済むことを、幼い頃に知ってしまった者同士。おそらくは政宗も、それをこの少女に見たのだろうと今なら判る。
「だから、それまでは秘密にしてくんろ」
教えたのは、小十郎さだけなんだ。と言う言葉に、この少女が心を開いてきてくれていることを感じて嬉しく思う。
「判った。その日までは、政宗様にも黙っておく」
ほら。と小指を差し出せば、いつきは不思議そうにそれを見つめ、それから小十郎の目を見た。
「ゆびきり。だ」
おずおずと、いつきの手が伸ばされる。その手を取って、小指を絡めた。
「小十郎さは、何でも知ってんだな」
おそらく、こうして誰かと約束を交わすのも初めてなのだろう。いつきは嬉しそうに微かに頬を赤く染めて、ゆびきりげんまん。と呟いた。
「何だよ小十郎、いやに機嫌がいいみたいじゃねぇか」
「そうですか」
そうだよ。と返して、政宗はいぶかしく思う。そういえば今日はいつきも、どこか機嫌が良かったように思う。二人は午前中に連れだって小十郎の畑に行ったと思ったのだが、それで何故、揃って機嫌がいいのかが判らない。
「何かあったのか?」
多少の皮肉も込めて愛想よく聞いてみれば、ふっ、と小さく笑われた。
「What?」
馬鹿にされた訳ではないのだろうが、なんだか面白くない。しかし小十郎はそれに気付いているのかいないのか、すぐに判りますよ。とだけ言い残し、下がってしまった。
「何なんだよ、一体・・・」
何だかおいてけぼりにされたような心持ちで、八つ当たりするかのように、政宗はやや乱暴に筆を走らせた。
パタパタと軽い足音が廊下から聞こえる。今この城の中であれだけ軽い足音をさせるのは一人しかいない。何があったんだ。と思いつつ、その足音を聞いていると、今度は遠くから、いつきの声と小十郎の声がする。
「・・・何だよ」
二人が最近打ち解けてきているのは知っていたが、走って行くほどにいつきが彼を慕っているとは思わなかった。いつの間にそんなに仲良くなったんだ?と思う反面、なんだか一人仲間はずれにされたような疎外感も少なからずある。
「政宗様」
声をかけられても素直に出る気になれずに、わざとのろのろと襖を開ける。
「少し外に出られてはいかがでしょう」
涼しい顔でそう言う小十郎の後ろに隠れるようにいつきがいて、一体何企んでんだか。と思いながらも、政宗は二人について行くことにした。
二人の後をついて歩いていると、一度ここまで来ていたのか、雪の上に小さな足跡が先に続いているのが見えた。
「一人で歩き回ってたのか?」
何気なく聞いてみれば、いつきは申し訳なさそうに俯いて小さくうなずく。別にそんなに怯えなくとも。と思うのだが、もしかしたら、気付かないうちに不機嫌なのが声に出ていたのかもしれない。
「殿様、こっちだべ」
いつきが指さす先を向けば、白い雪の中に浮き上がるような色が見えた。
「へェ・・・Adonis か」
黄色い花が、雪の中から顔を出している。雪に埋もれるこの地で、白と黒以外の色を見られる機会はそう多くはない。
「こりゃ縁起がいいな」
軽く口笛を吹いてそう言えば、嬉しそうにいつきが笑う。
「気に入ってくれただか?」
Yes. とうなずけば、少女は寒さで赤くなった頬を両手で包むようにしながら、笑顔を返してくれた。
「良かっただ〜」
苦笑して、その銀色の髪をくしゃくしゃと撫でる。これを見せるために、寒いのに朝からここに来たのだろう。頬も鼻の頭も赤くなっている。
「とにかく一度帰って、あったまった方がいいな」
しばらく雪の中に咲き誇る花を見ていたが、そう言っていつきを促す。城に戻れば、温かい甘酒が用意されていた。どうやら小十郎が、出かける前に台所に伝えていたらしい。
「・・・で、何で黙ってた」
「お気付きでしたか」
「そりゃあな」
ここ数日、いつきが上機嫌だったりそわそわと落ち着かなかったりした原因があれだとすれば、しょっちゅう小十郎の元を訊ねていた理由も判ってくる。第一、いつきと一緒に外に出る人物なんて、今のところかなり限られているのだ。
「約束をしましたから」
へぇ。と、つぶやくように返して、それから政宗は座り込んだままむすっとしたように、窓の外を眺める。
「どうかしましたか?」
「あいつ、お前のことは小十郎って呼ぶんだよな」
それは政宗様や他の者がそう呼ぶからでしょう。というのはもっともで、しかしなんだか納得がいかない。
「殿様。と呼ばれるのは嫌ですか」
「・・・それか」
城の者達は、城の中では政宗のことを殿様。とはあまり呼ばない。政宗様。と呼ぶ。いつきはいつだって、一呼吸おいてから「殿様」と呼ぶ。おそらくは「お侍さん」と咄嗟に呼んでしまいそうになるのだろう。よく言い直しているのも知っている。
「殿様なんて、どうも堅苦しくていけねぇ」
そうかそうか。と、一人頷いている政宗を見ながら、小十郎は微かに込み上げて来る笑いを抑えた。
その日、いつきは政宗直々に「殿様と呼ぶのは禁止」と言い渡された。それなら。と、小十郎達と同じように「政宗様」と呼んだら、それも堅苦しいから、呼び捨てでいいぞ。と言う。
少し困ったのだが、子供が遠慮するな。と押し切られてしまった。しかし実際口にしてみれば、成程確かに、それが何よりも彼なのだ。と思えたから、その日からいつきは政宗のことを「殿様」と呼ぶのをやめた。
いつきが政宗に福寿草を見せてあげる話を書きたい。というのがきっかけだった筈なんですが⋯途中からなぜかこじゅいつ風味(?)に・・・
この前の外伝3は、この後の頃の話になりますね。
お侍→殿様→政宗
と、慣れてくるにつれ、呼び方が変わっているということで。
PR
天野宇宙にコメントする